第一部と第二部は楽園の烏の発行前後で分けています。
第一部
主要人物
第二作目以降の主人公。
北領・垂氷郷(たるひごう)郷長・雪正の次男坊。
【年齢】
五月生まれ。寛烏六年正月の時点で13歳、五月で14歳になる。※公式のおまけ冊子より。
【一人称】
一人称は「僕」であったが勁草院同僚には「俺」と言っている。また基本目上の者や初対面の者には「僕」だが威嚇する時にも「俺」と言うこともある。勁草院の院士相手には「私」と言っている。
【生い立ち】
雪馬、雪雉とは腹違いで雪哉の母は北家当主・玄哉の娘であり、れっきとした宮烏であるが本人は自分を北家の人間として見られる事を嫌がり身分の高いことを隠したがる。何よりも故郷の垂氷と家族を大事に思う。尚、北家の姫白珠や喜栄とはいとこにあたる。
【家族構成】
父:雪正
母:梓(育ての母)
兄:雪馬(一歳年上・腹違い)
弟:雪雉(五歳年下・腹違い)
産みの母:冬木(北家当主の娘)
祖父:玄哉(北家当主・羽林天軍大将軍)
元山内衆の叔父がいる。
【経緯】
横暴に振る舞い乱暴を働いた同じ北領の宮烏・和麿に新年の席で策を謀り報復した事をきっかけに和麿の代わりとして宮仕えをする事に。
近習として若宮に一年仕えた後に辞任、その後故郷の垂氷へ戻り大猿の襲撃事件を経て寛烏八年に勁草院に入峰、寛烏十一年桜月に首席で卒業、山内衆となる。
【風貌】
茶色を帯びた髪(よく肥えた土と同じ色)で癖っ毛(猫っ毛)、茂丸は「たんぽぽの綿毛のような頭」と表現している。
これといって特徴のないどこにでもいるような面差しであり美青年ではない。
小柄で勁草院入学当時も一番小さく最前列に並んでいたが卒業する頃には逞しく成長する。成長後の体つきは父親譲りだが基本的には母親似。
阿部先生曰く「雰囲気イケメン」
【性格】
育ての母親・梓をはじめ、家族を守りたいがために優秀である事を隠し“ぼんくら”を装ってきた。
そのため、垂氷では「郷長のとこのぼんくら次男」として変な有名人。
愚かな振りをしているが実は大変頭の切れる人物で、和麿をはめた事をはじめ、若宮の無茶な言いつけも全てこなし、また水やりの理由の意図もしっかり見抜く。敦房の暴挙の際や第三の門にて一人で切り抜ける場面では最良の判断を導き出している。
初めは若宮の考え方に同意できず、また雪哉は自分が北家の人間として見られる事を嫌っていたため“北家の雪哉”として利用された事に腹を立てていた。また、一年間の近習を終えた後再度味方になって欲しいと若宮に言われた際には「僕の知らない所、僕と関係のない所で、どうぞ勝手に死んでください」と返している。
大猿の襲撃事件をきっかけに“真の金烏”の事や若宮の立たされている状況を理解し考え方を変え、若宮に忠誠を誓うようになり若宮を朝廷内部から護るために勁草院入峰を決意する。またこの頃から「利用できるものは最大限に利用する」という割り切った考え方をするようになる。
恋愛においては冷めており、嫁にする女の条件として聞かれた際に好みよりも政治的な部分を最優先に挙げる等、恋愛感情がはなからなく、嫁という立場について「美人を抱きたいなら花街に行きゃいいじゃないか」と、かつての若宮が妻選びの際に言った台詞と同じような事を言うようになる。また、あざとい女性を見てきたせいか小梅の好意的な態度をはなから信用せず警戒していた。女性関係ではないが治真から慕われていた際も最初は裏があるとさんざん勘ぐっていた。
外面がよく、判で押したような作られたにこにこ顔をするがその内面は腹黒く、仲間からも「性格が悪い」とよく言われる。
市柳は雪哉を「能天気を装った邪悪な笑顔」「人畜無害そうな表情を裏切る狡賢く光る恐ろしい双眸」と表現している。
【得意分野】
一度見た顔は忘れないと言っている事や、勁草院では兵術の演習の際に一戦前のサイコロの出目を全て暗記していた事から記憶力がずば抜けて優秀。目(動体視力)も恐ろしい程良いと言われている。
勁草院では頭角を現し体術、用兵術、弓射を得意とする。
体術においては先に手を出さず出された手足を捕らえて関節を決める戦い方をする。
用兵術においては勁草院一年目で兵術教官を打ち負かし、二年目で羽林天軍現役上級武官を打ち負かす腕。一年目で当代最高の軍師・翠寛を破った事から「麒麟児(きりんじ)」と呼ばれている。
弓射では端午の節句の花形射手に抜擢され難なく大役を務める。
【苦手分野】
自身は優秀なのだが他人にものを教えるのが信じられないぐらい下手で、勁草院にて同輩に勉強を教えようとしたが意思の疎通が図れず教えるのを断念し、課題を移させてあげる事に変更せざるを得なくなった。雪哉自身も教えるのが下手だとこの時まで気がついておらず「想定外だ。まさか、こんなことで自分の無力を痛感する羽目になるなんて!」と言っている。
【酒について】
北領の武家のしきたりで「産湯の代わりに酒に浸からせる」というものがあるため年齢に関係なく既に酒は飲み慣れている。めちゃくちゃ強く、下手すると酒と水の区別がつかないレベル。
【好きな食べ物】
勁草院にて怪我をした明留に茂丸がお見舞い品に“李(すもも)”を持ってきた際「俺、李好きなんだよね」と言っている。
また、若宮と縁の深い“金柑”も好んでいるように見える。
【金柑(きんかん)について】
近習時代に若宮から砂糖をまぶした干し金柑を度々“働き分”として貰っていた。良い仕事をした時はまとめて5、6個貰うこともあった。大紫の御前に「何か欲しいものはあるか」と聞かれた際も冗談めかして金柑と答えている。その際若宮と金柑を重ねたかのように“くせが強くて、むしろあまり好きではない。だがおかしな事に、決して嫌いではないのだから困る。投げて寄越されるなら、なおさら良い”と考えている。勁草院時代には雪哉が明留に金柑を差し出している。これは若宮化したとも取れるし金柑を好んで食べるようになったとも取れる。また金柑が出た事で明留を引き込む一連の作戦の背後に若宮がいるという事を暗喩しているとも取れる。金柑自体は若宮お手製。(※公式Twitterの一問一答より)
金烏代(きんうだい)・今上陛下と側室西家の姫・十六夜との間の子。一人称は「私」。
真の金烏(しんのきんう)とされる日嗣の御子(ひつぎのみこ)。若宮殿下と呼ばれる。谷間(たにあい)の賭場や仙人蓋(せんにんがい)の調査で垂氷へ出向いた際には墨丸という偽名を使っている。
寛烏六年二月の時点で17歳。
後ろ盾の祖父(先代金烏代・上皇)と母十六夜が亡くなってからは継承者争いから度々命を狙われ、自衛の為母の実家西家にて暮らしたり、また見聞を広げるという名目で外界に出て自身の力がつくまで暗殺の危険から逃れていた。
幼少期より毒を盛られる事が頻繁にあったため、体が弱く療養生活が常であった。様々な毒の味を舌が覚えているという特技をもつ。また大紫の御前対策として大紫の御前がよく使用している大量に用いると毒性をもつ香“伽乱(かろん)”を自身も度々使用して耐性を付けている。尚、伽乱は兄・長束から送ってもらい入手していた。
寛烏七年春に浜木綿を妻に選び正室とした。
【容姿・風貌について】
年の割には背が高く、17歳時点ですでに175㎝近くあった。体つきはほっそりとしたしており兄の長束と比べるとひどく華奢。髪は浜木綿よりは短い美しい長髪。『鳥形時と同じ艶やかな紫を帯びるほどに濃く美しい漆黒』『癖のない錦糸のような黒髪をうなじでひとまとめにしている』の記述。
黒すぎて紫水晶ように輝いて見える瞳に切れ長の目、面は白磁のように白く透き通った肌で女顔であるが眼光は鋭く抜き身の刀身のようにどこまでも鋭く凛と冴え渡った冷やかさがあり凄みをもっている。西家の母親似の容姿であり、妹の藤波とは似ていない。
やや高めの凛としたよく通る声。一挙手一投足に黄金の粉がこぼれ落ちるような気品があり怜悧な美貌を持つ青年。
鳥形姿は何羽かの馬に比べても並外れて大きく、日の光で青や緑に艶を変えて光っている。とんでもなく綺麗な大烏。
【性格について】
大事な儀式をすっぽかしたり花街へ頻繁に通い遊びまわっている事から“うつけ”と呼ばれるが、政治策略において長けた人物であり、すっぽかしも花街通いも意味のある行動である。
性格は飄々としており、合理的なものの考えで一般的な感情を理解し得なく冷淡で我儘とされるが、これら全て“真の金烏”の性質によるものという部分が強いので若宮本人の本来の性格であるのかは謎。※真の金烏の性質については用語一覧【真の金烏の性質】を参照。
【外界遊学と料理について】
外界へ遊学へ出ていた際は大天狗の潤天の家に居候しており、そこで炊事洗濯、子守りを覚えた。政治的なあれこれに比べれば家事は全く苦にはならなかったそうで、「特に料理が楽しかった」と後に述懐し、浜木綿を大笑いさせた。お菓子作りも好き。
料理を含むあれこれは潤天と彼の妻に教えられた他、大天狗に仕える烏天狗にも多くの手ほどきを受けた。
第五作目「玉依姫」では硬い南瓜をいとも簡単にさばき、志帆に料理の腕前を見せた。
【その他】
「墨丸」の名は浜木綿のかつて使っていた戸籍を流用したもの。浜木綿の身分回復が行われた時に、「墨丸」名義の戸籍の事務処理がうっかり行われなかったことに目をつけた奈月彦がうまいこと利用し使っている。
市柳とはまた違った意味で、ファッションセンスが壊滅的。
お酒は普通に強く、浜木綿の晩酌につい会える程度である。
—-
若宮殿下・奈月彦の護衛として仕える山内衆の青年。西領の有明郷出身の山烏(やまがらす)。
若宮とは幼馴染であり若宮が信頼を置く人物の一人。剣の腕前は大変優秀。時には自ら若宮の馬になる事もある。
小柄で色黒、その為少年のような外見。
身分が低い山烏でありながら勁草院を首席で卒業した経歴をもつ。
公の場では若宮に対し主従関係である口調で話し接するが他人のいない時は友人の様な口調で話す。
若宮の兄・長束の護衛の路近とはウマがあわず姿を見ただけで会話もせず早々に逃げ去る程。澄尾曰く「あいつは話が通じないから嫌いなのだ」と。
真赭の薄とは同じ西領のため、真赭が登殿していた頃は若宮の様子を探る手段として度々真赭に呼ばれていた。(※桜花宮は男子禁制の上、姫は元服を終えた男子に顔を見せてはいけないため代理の菊野(きくの)が桜花宮の外で話す場を設けた。)
浜木綿が入内してからは好き勝手する似た者夫婦の若宮夫妻の尻拭いを筆頭女房となった真赭の薄と共にする事でより親しくなる。
出家し恋愛に興味がなくなったがそれでも尚も美しい真赭の薄を勿体無く思い、良い縁談相手を見つけようとする若宮夫妻に雪哉を勧める。だが雪哉を弟のように思う真赭の逆鱗に触れ、二度と顔を見せるなと叱咤を受け真赭の薄の縁談は破談・白紙となる。
その実澄尾は真赭に好意を寄せていたのだが、身分が釣り合わないことから身分も腕前も申し分のない雪哉を勧めた。それを千早に感づかれ本音を少し零した。
元々片親で、勁草院に入る前に母は病でなくなっている。勁草院入峰は有明郷の郷長が後見人となって入峰。
寛烏13年の志帆が逃げた際の山神の暴走で奈月彦を庇い瀕死の重症を負う。山神の呪いにより攻撃を受けた左半身の回復が見込めず左腕、左脚を切り落とす事となる。その後志帆の癒やしの力によって呪いは解かれ一命は取り留めるが片腕片脚を失ったため護衛の任務からは引退する。
お酒の強さは人並み[一問一答より]。
奈月彦の腹違いの兄。兄宮。金烏代・今上陛下と正室・大紫の御前の長子で正当な後継者であったが奈月彦の方に真の金烏の素質があったため日嗣の御子の座から降り、山神さまに仕える身となる。院号は「明鏡院(めいきょういん)」。
本人は継承争いをする気がないにも拘わらず母・大紫の御前や母の実家南家がまだ長束を日嗣の御子の座に返り咲かせようと画策する。忠信の厚いと思われた敦房も「長束さまのため」と長束の望んでいない若宮暗殺を企てていた。
谷間と中央花街の中間に位置する場所に屋敷を構えている。
【容姿・風貌について】
・[烏は主を選ばない]新年の席での記述(雪哉視点)
硬質な黒髪。生まれの高貴さが現れたような優れて整った面差し。なよなよした雰囲気のない立派な体格の青年。
・[空棺の烏]入峰の儀での記述(茂丸視点)
それなりに背が高く見栄えが良い。背中には切り揃えられた長髪を流しており紫色の法衣の上に豪華な金の袈裟を纏っている。気品のある面差しをしていながら堀が深く武人のような厳しさも同時の持ち合わせている。
・「公式QA」より
髪の長さは出家したため奈月彦よりは短いが長髪。容姿は祖父(仙台の金烏代)似。
【その他】
側仕えはいるが近習(側近候補)と呼べるような者は存在していない。
お酒は普通に強い。奈月彦と同じぐらいの強さ。
長束の護衛。南領・南橘家当主安近の子。弟に公近がいる。勁草院卒業生で勁草院を首席で卒業した経歴を持つ。
【容姿・風貌について】
・[烏は主を選ばない]紫宸殿前での記述(雪哉視点)
傲慢が服を着て歩いているかのよう。
・[空棺の烏]入峰の儀での記述(茂丸視点)
大柄な茂丸よりもさらに大きい巨躯。衣の上からでも明らかな筋骨隆々たる体つき。身に纏う羽衣は褐衣(かちえ)の形をしているが頭に冠は付けていない。適当に縛られた髪の毛はまるで冬毛に覆われた狸の尻尾のよう。笑を含んだ口元からは尖った鬼歯が除き大きな鷲鼻とぎらぎら光る目がひどく印象的。
【その他】(※公式twitter一問一答より)
出家済であり、名目上は長束がトップをつとめる明鏡院に所属する神官という立場。
お酒はめちゃくちゃ強く、雪哉と同じく下手すると酒と水の区別がつかないレベル。
夏殿の姫。一人称は「アタシ」。背が高くしなやかな黒髪。目鼻立ちのはっきりした気の強そうな美人。豊満な胸回りと腰つきながら、すらりとした長い手足をもっている。肉館豊ながら婀娜っぽさを感じさせない女。寛烏六年四月時点で18歳。
夏殿の姫として登殿するが南家当主・融の実の娘ではなく養女として入った。本当の父親は融の兄に当たる煒で、撫子とは元々は従姉妹で義理の姉妹。
桜の君の座の争いの最中桜花宮から逃亡し身分を剥奪されるが真赭の薄の計らいで真赭の下女として宮中へひっそり戻り、そのまま若宮の妻となる。
本名は墨子(すみこ)。若宮とは幼少期(若宮が五~六歳の頃)に悪友として面識がありその時は「すみ」と呼ばれていた。
幼少期両親が処刑され身分を剥奪、生き延びるために「墨丸」と名乗り山烏の男児として南本家の菩提寺である慶勝院(けいしょういん)で育つ。
髪の長さは奈月彦よりも長い。
お酒がめちゃくちゃ強い。単純にお酒が好きなため楽しく飲める。
秋殿の姫。西家の一の姫。一人称は「わたくし」。兄弟は弟に明留(あける)のほか兄がいる。十六夜は叔母で若宮・奈月彦とは従兄妹である。寛烏六年四月時点で16歳。
他の追随を許さない程の別格の美女で、赤い光沢をもった艶やかな黒髪と匂うように艶めかしい薔薇色(しょうびいろ)の肌、熟れきった甘い果実のようなみずみずしい唇を持つ。派手好みできらびやかな衣服や装飾を好む。悪趣味とも言われている。気が強く気位が高いが馬鹿ではなく知識もあり、正しい考えを出せる人。
若宮が幼少期大紫の御前の攻撃から逃れるために十六夜の実家で暮らしていたので面識があり、幼い頃から「いずれは若宮の正室となる」と聞かされて育ったため自分が正室になると信じて疑わず若宮に恋焦がれていたが、桜花宮での一件で若宮に完全に幻滅して尼削ぎをし、正室の座を自ら降りる。また、初めは対立していた浜木綿の事を誤解していた事に気が付き和解し、浜木綿が身分剥奪の上追放となった際自分の下女として浜木綿を招き入れ、浜木綿が正室となった後は浜木綿の筆頭女房へと自らなった。
澄尾については、西領同士の同郷であり若宮の護衛という身分から澄尾づてに若宮の動向を探ったり、若宮への連絡を送ったりとする関係であった。浜木綿正室後は似たもの夫婦に手を焼く境遇が同じことから、いつも尻拭いをさせられる立場として仲間意識を持っているがそれだけである。
雪哉については弟のように思っており、端午の節句(雪哉が花方射手を務めた時のこと。既に真赭は浜木綿の女房となっていた)にて久しぶりに会った際成長した姿に驚きこそすれ、恋愛感情は全く抱かなかった。そのため自分と雪哉を勝手にくっつけようとした澄尾に大激怒し「二度と近づくな」と軽蔑の色を強く見せた。
お酒はあまり呑んだことがないので自分が強いか弱いかもよくわからない。
奈月彦と浜木綿の子。姫宮。顔のつくりは奈月彦似、目元の華やかさは浜木綿似。黒髪で大きな目。一度も笑わなかったが雪哉を見て初めて笑った。
雪哉と同室の友人で雪哉が親友と認める人物。北領・風巻(しまき)郷 佐座木(さざき)出身の平民。弟、妹がいる。一人称は「俺」。
母方の祖父が飢饉の際に「自分の娘を遊郭に売り飛ばすくらいなら」と世話になっていた地主の馬に自らなった。そのため茂丸はこの世に生まれてくることができたという生い立ちがある。
大猿による佐座木の下屋敷襲撃をきっかけに勁草院入峰を決意、勁草院へは塾頭と郷長の推薦で、あとふた月で十八歳になるというギリギリ入峰できる年齢で勁草院へ入った。勁草院入峰の際手荷物は風呂敷包み一つで鳥形で門前に乗り付けた。
雪哉が呼び始めた「茂さん」呼びが皆にも浸透し皆のまとめ役と目されている。
【容姿・風貌について】
・[空棺の烏]二号棟十番坊へ挨拶へ来た際の記述(市柳視点)
頭を鴨居にぶつけるほどの大入道のような巨体の大男で同輩の中では一番背が高く、また市柳や公近よりも高い。
日に焼けた顔はいかにも健康そうで、手入れのされていない太い眉毛は大きな毛虫のよう。丸っこい団子鼻と黒々とした瞳がともすれば恐ろしく見えてしまいそうな顔立ちを一転して優しそうな印象に変えている。その雰囲気は熊から獰猛な部分を全て抜き取ったかのようであり、いかにも気持ちの良さそうな青年。
寛烏13年の志帆が逃げた際の山神の暴走時、奈月彦の護衛にあたっており山神の攻撃を受けて死亡。
雪哉の一年上の同室の先輩。風巻(しまき)郷出身、郷長の三男坊で地方貴族。一人称は「俺」。
雪哉とは同じ北領で郷長家の息子同士、幼馴染のような間柄。だが仲良しというわけではなく苦い思い出のある間柄。再会した際に「忘れたくても忘れようのない記憶が蘇った」「容赦なく打ち据えられた痛みと、降りかかる罵倒の数々、判で捺したかのように変わらない笑顔に、気が狂ったかのような笑声のけたたましさ」と市柳視点の記述があり、昔雪哉に相当痛い目にあわされたと思われる。そのため市柳にとって雪哉は「悪夢」であり、自分の同室の後輩として挨拶された際に絶叫している。
寛烏八年の時十六歳。十五で勁草院へ入峰。勁草院へは雪哉が「自分は勁草院には行かないし、中央で宮仕えするつもりもない」とはっきり言ったのでわざわざ入峰した。
【容姿・風貌について】
・[空棺の烏]二号棟十番坊へ挨拶した際の記述(茂丸視点)
良くも悪くも今時の若者らしい若者で、以前は世を拗ねたところがあり、その服装の突飛さと共に郷民達から随分と心配されたものだったが、勁草院での修行を経て、今では立派な院生となったようである。もとより目つきと口は悪いものの性根の真っ直ぐな男。
【その他】
勁草院は後ろから二番目の成績で無事卒院。卒院後は雪哉が裏で推薦し、招陽宮の護衛の一人として働いている。(※公式twitter一問一答より)
真赭の薄の弟。一人称は「僕」。
幼い頃は腕白でよく外で遊んでは衣に穴を開けて帰ってくるので羽母(うば)に怒られたくないがために真赭に泣きついて衣を繕ってもらっていた。
【容姿・風貌について】
・[空棺の烏]家財道具を運び入れている際の記述(市柳視点)
つやつやとした赤茶の髪で丁寧に梳られている。市柳が今まで見た誰よりも端整な顔立ち。肌の色は曙光を浴びた咲き染めの白牡丹のよう。ぱっちりと大きな目は日に当たった泉のようにきらきらと輝いている。まるで女の子のような甘い顔立ちだが引き結ばれた唇ときりりとした眉が彼の美貌をただ大人しいものにしていなかった。利かん気の強さと自信の大きさを垣間見せる少年はただ美しいというだけでなく、人を惹きつける魅力が既に備わっているよう。見目良く佳麗。
南領・南風(はえ)郷出身。一人称は「俺」。
南風郷にいたころの名は“絋(こう)”。妹・結と共に南橘家の安近の元に仕えていたが雪哉の策で明留が二人の身柄の権利を買い取る。
結とは血が繋がっていないが妹として育てている。結との関係・絋の名から千早に名を変える経歴は【コウ・絋(こう)】の項目を参照。
【容姿・風貌について】
・[空棺の烏]試合形式の剣術演習の際の記述(茂丸視点)
寡黙そうな男で真一文字に結ばれた口は生まれてこの方一度も開かれたことがないがごときの閉ざしよう。上背がある体つきは均整がとれておりよく引き締まっているが面長な上に頬骨が尖っているせいかどことなく痩せて不健康そうに見える。顔に垂れた長い前髪の間から覗く三白眼はひどく鋭い。
勁草院関係
院生
【雪哉の同期】
勉強会仲間。東領の平民出身。勁草院三年目の記述で名前が唯一出てきていない。
勉強会仲間。平民出身。お調子者。地元では剣の腕は一番だったが独学のため形がなっておらず勁草院では素振りばかりさせられ、形がなっていない為と気がつかず不満を漏らしていた。
勉強会仲間。平民出身。普段は不平を漏らさない性格。
【雪哉の後輩】
寛烏十年入峰。雪哉の二つ下の学年。東領・鮎汲(あゆくみ)郷出身。そこそこ剣は使えるが他の勁草院生に比べて身体能力は劣る。勁草院入峰を希望して郷長の推薦ももらっていたが入峰適正手合いで負けたため入峰を諦めていたが、同じく小柄ではあるが優秀な雪哉の例もあると見た郷長にそのまま入峰を推薦される。
雪哉が草牙(そうが)の時、治真は鮎汲郷郷長に連れられ笙澪会(しょうれいかい)を見に行った。そこで羽林天軍の現役上級武官を打ち負かしている雪哉の姿を見て惚れ込み、入峰してからは雪哉に懷き雪哉の身の回りの世話を自ら進んでやっていたため周りからは“雪哉の舎弟”と言われている。
雪哉の嵐試の最終戦で雪哉の部隊に参加し荳兒(とうじ)でありながら別働隊の隊長を任される。その嵐試の最中に猿によって攫われたが無傷で雪哉らに助け出される。
寛烏八年入峰組。雪哉の一つ下の学年。雪哉の嵐試の最終戦で雪哉の部隊に参加。寛烏13年志帆が逃げた際の山神の暴走によって死亡。
寛烏八年入峰組。雪哉の嵐試の最終戦で雪哉の部隊に参加。
寛烏八年入峰組。雪哉の嵐試の最終戦で雪哉の部隊に参加。
『弥栄の烏』で名前のみ出る人物。鉄丙の仲間との事なので鉄丙らと同期かと思われるが詳細は定かではない。寛烏13年志帆が逃げた際の山神の暴走によって死亡。
院士
勁草院の頂点、教官達の長である院長。
【容姿(本文より抜粋)】
黒髪に白い筋の混じった六十半ばの男。神官の纏うような法衣の形に編んだ羽衣に濃紫に金の刺繍の入った懸帯を掛けている。体格は良いとは言えないが面差しは知的でありながらいかにも厳格そう。
年齢の割に深く張りのある美声である。
天景院(てんけいいん)の院主。金烏代の代替わりによって尚鶴から勁草院の院長職を継承するはずだった人物。
金烏(きんう)宗家
【宗家従者】
蔵人。東家の流れを汲む一族、東高倉の出自だが、傍流も傍流で取り立てられるまで東大臣と目通りさえしたことがなかった。先代の金烏代に気に入られ蔵人となったが、先代亡きあとは後ろ盾もなくなった。
ずんぐりむっくりとした体型で、唇は分厚く、金壺眼、もじゃもじゃの眉で、百歩譲れば精悍といえなくもないかもしれないが、貴族然とした女顔とは程遠く、無骨でやぼったい。貴族と言うよりも山賊に近いような面構え。
やわらかで、精緻なのに華やかな文字を書く。
松韻を女として扱い、妻にしようとした。処刑されそうになった松韻を助けるため芝居をして鮎汲郷へ祐筆として左遷された。しかし松韻は処刑されることを選び、忍熊は彼女が忍熊との間に宿し、産み落とした卵を受け取った。
楓蚕の後を継ぐはずだった藤宮連。男と駆け落ちしようとしたことが大紫の御前にバレて自死を命じられた。
捺美彦の秘書官の落女。松韻という名は男名。元皇后付きの女官であるため今上陛下の秘書官ではあるが実際には大紫の御前に忠誠を誓っている。すっきりと整った顔立ちをした意志の強そうな吊目の女。男と同じ文官装束だが冠は付けていない。黒髪はばっさりと切られて首筋にもかからないほど。藤宮連(ふじみやれん)にも所属している。
出生時の名は「まつ」。谷間の女郎宿の布団部屋で生まれた。不器量な母に似ず、「小作りな顔の中で吊り上がった目と、淡い鴇色をした小さな唇が品よくおさまり、後頭部の形はつるりと丸みを帯びて、すっきりとした首元は幼いながら既に色気が感じられた」。美人で聡明であったが、男嫌いで可愛げがなく、歌舞音曲に興味がないため、女郎屋のものは彼女をもてあました。書の特にかな文字でなく真書に強く興味を持ち、その流れで学問好きとなったことで楓蚕の目にとまり、落女となる道を選んだ。大紫の御前に「松韻」と名付けられ、忠誠を誓った。
書を得意とし、古式に則った正統かつ男らしい筆さばきである。
秘書官として正面切ってやりあう仲であった忍熊に求婚され、政治的な判断で還俗することが決まるが、後輩順が「以前から忍熊と逢引きをしていた」と嘘の証言をしたために大紫の御前の怒りを買い、処刑が決まるが忍熊の機転で放免となる。しかし、復官の条件として大紫の御前から胎の子を堕ろすよう命じられるとそれを拒み、自分と忍熊は愛し合っていたと言って、卵を産み処刑されることを選んだ。
【過去の人物】
女性(雌烏)。元は烏神。
北領
【垂氷郷(たるひごう)】
【北家(ほっけ)】
北家当主であり、羽林天軍(うりんてんぐん)を取り仕切る大将軍(たいしょうぐん)。北大臣玄哉公(きたのおとどげんやこう)と呼ばれている。白珠、雪哉は孫にあたる。
根っからの文官である他三家とは違い、己は武人あるという誇りを持っており、煮え切らないやり方を好まない。そのため策謀は縁遠い人である。顎鬚がある。
北家当主の直系の孫。いずれ北家当主の座を引き継ぐことが決まっている健康的な肌色の青年。寛烏六年に二十三歳となる。
雪正とは叔父・甥関係、雪哉とは従兄弟関係にあたる。中央にある朝廷に勤める官人、部署は兵部省(ひょうぶしょう)。
宮仕えをする事になった同郷の雪哉に親切にしてくれる。
北家次期当主。
【北家従者】
北家の屋敷に仕える庭師の息子。北領出身の山烏(やまがらす)。
特別顔立ちが整っているわけではないが優しげな情の深そうな目をした若者。
第一作目【烏に単は似合わない】の最後の桜花宮の場面では「若宮より背が高くひょろりとしている」とあるが、第二作目【烏は主を選ばない】の端午の節句の場面では「雰囲気から武人ではないが体つきもしっかりしていおり軟弱な印象はない。」とある。
年齢は寛烏六年で十七歳、白珠より三つ年上。十二の頃に庭の手入れのため父親に連れられて北家に行った際に初めて白珠の姿を見て一目惚れをした。
白珠とは主従関係ではあるが幼馴染のため白珠にとって愚痴をこぼせる友人のような存在。白珠に恋心を寄せ、白珠の登殿が決まった際に駆け落ちを切り出すが断られている。
寛烏六年、白珠が登殿してまもなく勁草院の下働きとなり若宮の情報を桜花宮にいる白珠へ文で報せるという名目で白珠と繋がりを保つ。また、白珠の様子を見せてもらう事を条件に若宮に手を貸し、同年の端午の節句では若宮に連れられ桜花宮に潜入し、遠目から白珠の姿を見ている。その後冬頃、再度桜花宮へ潜入し白珠に駆け落ちを持ちかけ、白珠を待っていたが白珠は現れなかった。最終的には若宮の計らいで宿下りをさせられた白珠と共に暮らすことが叶った。
白珠の女房。老婆。太め。
【北四条家(きたしじょうけ)】
【風巻郷(しまきごう)】
南領
【南家(なんけ)】
浜木綿の母。十六夜を亡き者にしたとされ追放、秘密裏に処刑された。
【南家従者】
夕虹の羽母の一人。南家末席の下働きの女。
【南風郷(はえごう)】
千早の昔の名。昔から家族ぐるみで付き合ってきた関係のヌイがまだ卵から孵っていない結を絋に託して斬足(ざんそく)され、その夫・ショウジも死刑となったために二人に代わり結を妹として育てる。
絋の両親は結が五つになる前に、過労で体を壊した母の看病のため仕事を休んだ事で父は斬足させられ、母もその失意のまま亡くなった。
結がヌイの子であることが地主らにわかると結が斬足されてしまうため地主に隠して生活しており、また南風郷の小作人仲間にも守られながら暮らしていた。結が八歳の時、地主の息子に犯されかけた際に絋が地主の息子の頭をかち割ってしまい、小作人仲間にも逃げるよう言われそのまま絋と共に南風郷から逃亡する。十日ほど山中を逃亡した後に領内警備の兵に捕まるが、絋の腕を高く評価した南橘家の安近に山内衆になる事を条件に身柄を所有される。その際新しい戸籍を用意され“千早”と名を変える。
【南橘家(みなみたちばなけ)】
西領
【西家(さいけ)】
赤茶色の口髭をもつ。
顕彦の正室。
【西家従者】
背が高めで立ち姿の美しい女。真赭の薄の元ねえやであり、彼女のことを「愛する主」として敬愛している。桜花宮登殿の際には真赭の薄付きの女房として、浜木綿入内後は真赭の薄の右腕として桜花宮で働く。
東領
【東家(とうけ)】
春殿の姫。薄い茶色の巻き毛、明るい髪の色と瞳をもつ東家の二の姫。音楽の才に長け愛くるしい面差しを持った才媛。浮雲の子。琴が得意で母・浮雲と同じく取り扱いの難しい“長琴(なごん)”を演奏することができる。一人称は「私」。寛烏六年四月時点で18歳。
箱入り娘で隔離されて育ったので世間知らずでおっとりしていている為「悪気は無いし仕方がない」と許されるキャラ。しかしあせびは「悪意が無ければ全てが許される」という事を知った上で自分の幸せの為に動いてくれる者を不幸にするあざとい女であり、協力者であった早桃と嘉助を死に追いやった張本人であった。それを若宮に見抜かれ窘められる。若宮はあせびに宿下がりを命じる際に「美しいとは思うがあなたのことが嫌い」と言い放っている。
登殿するまで仮名がなかったが『馬程度の下賤の者ならお前の色気に酔いしれることだろう』と侮辱の意味を込めて“馬酔木(あせび)”という名を大紫の御前がつけた。
双葉は姉であるが実はあせびは東家当主の子ではないので双葉と血の繋がりはない。実の父は倫。
あせびの父・双葉の父であるがあせびは本当の実の娘ではない。人の良さそうな笑みを浮かべながらのらりくらりと最後まで曖昧な態度をとり続け最終的には決定権を自分で握れるように仕向けるのが得意で計算高いため“腹黒”と言われている。
東家当主の娘。もともとは双葉が登殿予定であったが体を壊し“あばた”ができた為あせびが登殿することに。実のところあせびが嘉助に襲わせた(嘉助はあせびだと思っていた)事が原因。
真赭の薄の婿候補として名前が上がった人物。東家の者で正室が既にいる。
【東家従者】
東家の女房。あせびに仕える。経験豊かで四十路(寛烏六年ごろ)。元浮雲の女房。一人称は「あたくし」。
東家の下男。あせびに好意を寄せている。字の読み書きができない。一人称は「俺」。
仙人蓋(せんにんがい)関係
猿に襲われた栖合でたった一人生き残った少女。14・5歳ほどの小柄な娘で、大きな猫目につややかな栗色の髪、桃色の小ぶりな唇を持つ美少女である。
宮烏に憧れを持っており、梓曰く、お調子者で誤解を受けやすい性格をしているが悪い子ではない。
言葉遣いは蓮っ葉で気の強い性格であり、ろくでなしの父親の尻をはたきながら働かせ、自身も湖畔の店などで身を粉にして働いていた。口では父親のことを悪し様に言ってはいたものの、自身の唯一の家族であり自分を一番に愛してくれた治平を彼女も大切に思っており、父親の死を知った時には絶叫し遺体に取り縋ろうとした。
また、雪哉に好意を持っており、思わせぶりな視線を送ったり好かれようとしていたが、それは反対に雪哉の彼女への警戒を強める結果となった。
小梅の父親。借金ばかり作っており、代々守り所有していた楽泉水(らくせんすい)の湧く井戸を枯らす。小心者。
小梅の母であり、小梅によく似た顔立ちの、若作りで気の強そうな美人。髪色はつややかな栗色で、一人称は「あたし」。不遇な境遇に育ったことから自分を一番に愛してくれる存在に執心し、そのために治平や小梅を見捨てて別の男と再婚した。仙人蓋を得るために治平に辺境への猿の手引をさせ、彼に全ての罪を被せようとするも、事が露見。霜原の宿にて若宮を刺し、夫と共に逃げるも捕まり、処刑される。
谷間関係
地下街(ちかがい)の頭領。谷間を治める親分達の中で最も力のある男。
谷間の遊郭の遊女。
人外(山神・猿・天狗等)
【山神】
宝の君。山神であるが実のところ半身であり山神の荒魂(あらみたま)。『椿』の名は志帆が付けた。
憎悪に満ち猿と人間の合いの子のようなおぞましい容姿となっていたが、志帆の愛を受け本来の白い髪の美しい容姿取り戻す。力の制御ができず癇癪を起すと無差別に周りにいる者を殺してしまい、また御供の女が玉依姫を全うできなかった際は女を喰い殺していた。だが志帆が玉依姫となり母親となってからは、すぐに怒る事も人間を喰らうこともしなくなった。
完全な山神ではなく半身の荒魂の為、落雷や地震、炎など神の力で全てを破壊することはできるが癒すことができない。
椿が放った炎に焼かれた火傷は単なる火傷ではなく、薬では治せずじわじわ命を奪ってゆく呪いがかけられている。椿の感情によって痛みを増したり症状が進行したり、また改善したりするが深手を負っている者は椿の感情ではどうにもならない。
成長が早く、志帆が神域に連れてこられた際は二歳児ぐらいであったが食事を与えて生活するうちに十日も経てば五、六歳児ぐらいまで成長した。その後も成長を続けるが志帆に甘えたいために子供の容姿のまま姿をとどめていた。最終的には十八歳ぐらいの容姿にまで成長した。
先代の山神は二十を前に成長を止めている。
銀髪の少年。椿の半身、山神の和魂(にぎみたま)。二匹の仔犬を連れている。
英雄の連れている白い日本犬の仔犬。神域へ戻る志帆に預け、志帆が『モモ』と名付けた。やんちゃで怖い物知らず。正体は狛犬。
英雄の連れている猟犬の大犬。正体は獅子。
【猿】
猿一族の長。大猿。黒髪の雌猿。元は猿の神。
小さな老いた猿。御内詞(みうちことば)を話すことができる。人間を食べていないので体が小さいままで力もない。先代の金烏那律彦と面識があった。
幼い子猿。『黄金の烏』にて雪哉が隧道で猿の領域に辿り着いた際に襲ってきたため若宮が斬り殺した。
ヨータの兄。目の前でヨータが斬り殺されたため雪哉と若宮に恨みを持っている。弟が殺された時マドカは九歳。
山内に猿が攻め入る際に間諜を買って出た猿。八咫烏に子供を殺されており恨みがある。
【天狗】
人間界で暮らす大天狗。銀縁の丸眼鏡をかけた三十代ぐらいの気のよさそうなおしゃれな男性。茶髪にパーマをかけており鼻にはそばかすがある。煙草を吸う。
人間界では東京住まいでいくつもの会社を経営している社長。龍ヶ沼に面した場所にロッジ風の別荘を持っており、そこへ避暑に来ていた際神域から逃げてきた志帆と出会う。奈月彦とは馴染みであり外界(人間界)の道具などを八咫烏らへ売る商売をしている。
白髪が増えてきたようで白髪染めによって以前より髪色が明るくなっている。
潤天の部下の烏天狗。気の良さそうな中年の男。
人間界
都内で祖母と二人暮らしの小柄な高校一年生。十歳の頃両親が交通事故で他界。叔父の修一に誘われ祖母、母の故郷の山内村(さんだいむら)の祭を見に村へ行くが山神様の人身御供として生贄にされてしまい神域にて山神の母『玉依姫』となることになった。
志帆の祖母。山内村出身。厳格で責任感が強く、頑固な性格。
十九の頃に山内村に嫁ぎ、長男の修一と長女の裕美子を産む。しかし三十七年前、夫が裕美子を生贄にしようとしていることを知り、娘を連れて逃げ出す。その後女手一つで娘を育て、娘夫婦が事故死した後は孫娘の志帆と同居していた。志帆が御供にされた後は奈月彦や谷村と協力して志帆を連れ戻そうとするも、怨霊と化したサヨに心臓を握り潰されて亡くなる。
志帆の母、久乃の娘であり修一の妹。山内村に住んでいたが御供にされるはずだったが身を案じた母・久乃に村から連れ出される。その後東京で暮らし志帆を産み育てるが、志帆が十歳の頃交通事故により夫と共に他界した。
山内村に住む志帆の叔父。久乃の子で志帆の母(裕美子)とは兄妹。五十近くの中年の男性。十歳の頃に母・久乃が妹を連れて村から逃げ捨てられた。
修一の娘。小学校低学年くらいの少女。
修一の息子で彩香の兄。中学生くらいの男の子。
一度朽ちた山神を蘇生させるために御供になった女。玉依姫となり山神を産み落とすが気味悪がっており、山神を邪険に扱う。村に残した婚約者・幹次郎と逃げ出そうとするが失敗し大猿に殺される。
英子の婚約者。一度神域に行ってしまった英子が村と神域の境界まで降りてきた際に一緒に逃げ出そうとするが、失敗し大猿に殺される。
英子の次に玉依姫となった十歳にも満たない少女。山神とうまく関係を築き信頼関係を持つが、母の危篤の知らせを受け必ず戻る事を約束し村に一度帰る許しを貰う。村へ下り葬儀が終わればすぐ神域へ戻るつもりでいたが、山神から逃げ出してきたと思い違いした村人たちにより再度生贄とするため龍ヶ沼に沈められ死亡した。
その後他の女が玉依姫となる事に嫉妬し後任の者が玉依姫にならぬよう、魂魄のまま神域から逃がす手引きをする。しかし志帆だけは自ら戻ってきてしまい、山神が信頼する一番の玉依姫へとなってしまった為に嫉妬に狂い怨霊となった。
志帆を自分と同じ目に合わせ、あの時山神の元へ帰れなかった真実に気づかせるため志帆の祖母・久乃の心臓を握りつぶし殺した。
最後は山神・椿によって浄化された。
第二部
主要人物
たばこ屋 カネイの店主であり、荒山の権利者である。安原作助の四番目の養子で、他の兄姉とは親子ほど年が離れている。十歳になる前に安原作助に引き取られた。引き取られたばかりの頃に、山の中に一人で放置をされる。その後は、安原作助のめちゃくちゃな旅に付き合わされ、賭場によく行っていた。大学生だった頃に行きつけのたばこ屋を買い取り、家族に相談もなしで大学をやめた。タバコ好きで特にもらい煙草が好き。
一人称は「俺」
【容姿・風貌】
[楽園の烏]での記述
伸ばしっぱなしのワカメのような黒髪に、無精ひげの浮いた顎、眠そうな垂れ目、首まわりがぶよぶよになったTシャツにジャージのズボン姿だ。咥え煙草とごつい金のネックレスも相まって、自分で言うのもなんだがめちゃくちゃに柄が悪く見える。
神官のふりをするために真っ白な神官の装いをしたが悲しいほどに似合っておらず、トビに「ちょっと薄汚れてるくらいの方が似合っている」と言われた。
北家系列の北小路家の長子。尊敬していた父が気に入っていた雪哉に憧れ、七つになって挨拶に行った時に雪哉の部下である治真に山内衆になることを勧められた。大変優秀で勁草院を首席で卒業。山内衆になって最初の命令で留学を命じられ、三年間外界に出ていた。留学から帰ってきて半月後に安原はじめの案内役として任命された。治真のお気に入り。
外界で一番おいしかったものはハンバーガー。
一人称は「私」。安原はじめからはヨリちゃんと呼ばれており、はじめちゃんでいいよと言われたがはじめさんと呼んでいる。
【容姿・風貌】
[楽園の烏]での記述(はじめ視点)
年は二十代前半だろうか。黒々とした眉のけざやかな、やや目尻の垂れた甘い顔立ちのイケメンである。(中略)髷を結えるほど長髪な者ばかりの中で、彼だけ髪が短かった。しかも単に短いというだけでなく、そのまま東京の人ごみにいたとしても不自然でない髪形をしているのだ。
自らをかつて殺された幽霊だと自称する、安原はじめを山内に連れて行った人物である。その目的を自分や自分の両親、大切な人達が殺されたことへの復讐だと安原はじめに語っている。安原作助とトビとの接点あり。安原はじめを山内に連れていく際に大型トラックを運転した。
【容姿・風貌】
[楽園の烏]での記述(はじめ視点)
点滅する古ぼけた街灯の下、光の輪が浮いたストレートの長い黒髪が、夜風を受けて豪奢に舞っている。シンプルな白いワンピースをまとった体は、細身なのに腰がくびれており、長い手足がすんなりと伸びていた。
そこに立っていたのは怖気をふるうような美女であった。
(中略)
何よりも彼女を非凡にしているのは、そのよく輝く目であった。
満天の星のきらめく、瑠璃色に澄んだ夜空のような瞳をしている。
形のよい骨格の中で、はっきりとした、目元だけが異様なほどの存在感を放っていた。彼女の持つ意志の強さが、きらびやかな瞳を透かして見えるようだ。
報告書によると十代後半から二十代、身長は五尺五寸前後。
第一部の雪哉と同一人物。黄烏であり普段は黄烏の尊称である博陸侯と呼ばれることが多い。博陸侯以外にも閣下や雪斎公と呼ばれることもある。黄烏になるためには便宜上出家する必要があり、独身である。
楽園の烏(およそ2015年)より十年以上前に外界に留学経験あり。その際は北山雪哉と名乗っていた。
【一人称】
第一部では「僕」が主であったが、第二部では「私」と言っている。
【風貌】
[楽園の烏]での記述(はじめ視点)
今まで忙しなく動いていた男達よりも上等に見える和服を着た者達と、黒装束の若者達だ。その腰には、時代劇でしか見ないような大きな日本刀まで吊るされている。
先頭を悠然と歩むのは、上品な風貌の中年男性であった。
感情の読めない笑みを浮かべた面差しだけみれば、高僧か、あるいは大学教授とでもいった風情である。
ゆったりとした黒い着物に、豪華な刺繍のされた金の袈裟をまとっている。年は四十くらいだろうか。筋肉のはりの感じられる体つきはそれよりも若いようにも見えるが、穏やかに微笑む顔には深く皺が刻まれ、肩にやわらかく流した長髪には白い筋が混じっているあたり、年齢不詳の感があった。
第一部での説明はこちら。奈月彦と浜木綿の娘で内親王。淩雲山紫苑寺にて生まれ育ったため、紫苑の宮と呼ばれている。彼女を女金烏にするという動きが当時の金烏と長束を筆頭にして進められていたが、当時の金烏の崩御と凪彦の存在が明らかになったことで頓挫した。それと同時に翠寛とともに逃亡した。
【容姿・風貌】
[追憶の烏]での記述(雪哉視点)
まっすぐにこちらを射抜く瞳は黒々と澄み切っており、その輝きが何とも眩しかった。大きな目を縁取る睫毛は影が落ちるほどに長く、笑みの形を描いた唇は小さく稚い。ただ可愛らしいだけではなく、その面差しには父親譲りの高貴さが色濃く表れ、もうすぐ八つになるという年齢からは考えつかないほどに表情は大人びている。
真赭の薄と澄尾の双子の片割れ。幼いころは病弱で、名医を訪ねるために山内中を回っていた。落女になった三年後に西家当主が推薦者となり貢挙を受けている。澄生は男としての新たな名前である。
【容姿・風貌】
[追憶の烏]での記述(雪哉視点)
癖一つない漆黒の髪は無残なほど短く、首筋にもかかっていない。 質の良い青磁の上下を一部の隙もなく纏っているのに、遊女のように真っ白いうなじが丸出しで、それだけで見た者の腹の底をぞわぞわさせた。 眉は、すうっと筆の先でなでたようにやわらかな弧を描き、唇は珊瑚色で艶がある。そして、何より印象的なのはその目だった。 目尻はきりりと色が濃く、長いまつげの影が落ち、瞳は銀河のように吸い込まれそうな色をしている。 まさに玲瓏たる美女と言うにふさわしい風貌である。
貢挙の任官試験で姿を現したとき、一度でも[[先代の真の金烏>#nadukihiko02]]の玉顔を拝したことのある高官は彼と瓜二つの娘を前に幽霊にでも出くわしたかのような面持ちになった。
山内衆
【勁草院(けいそういん)】
第一部での説明はこちら。奈月彦の代の勁草院の副院長だった。路近の件で相談に訪れた長束に翠寛を側近に迎えるよう助言し、翠寛が側近になるよう紹介状と無記名の手紙を渡した。
長束様は赤ん坊です。あなたが育てて差し上げなさい。
薬種屋七清の次男坊の清良として生を受け、南橘家の推薦で勁草院に入峰した。卒院後に挨拶をする為に南橘家に訪れた際に路近と対面し、路近が勁草院に入るきっかけとなる。その後、路近の教育をするために勁草院の院士となり出家し、清賢と名を改めた。路近から日常的に暴力を受けていた同室だった翠を別室に移し、翠のために自室を開放した。一方で路近との対話も積極的に行った。夕方に路近が翠を殴ったのを止めに入ったのをきっかけにどうして人は殴ってはいけないかという話から一晩中語り合い、朝にはうまい麦饅頭の焼き方を路近に懇切丁寧に説いていた。死ななければならない者などこの世に存在しないという考えを持ち、谷間で問題を起こした路近の代わりに右腕を失った。
【容姿・風貌】
[烏の緑羽]での記述(長束視点)
髪は神官にしては珍しく緩くまとめられており、笑い皴の刻まれた面差しと合わせて、とても勁草院の院士には思えない。すでに五十も半ばを過ぎたはずであり、年相応の見た目ではあるのだが、その表情は初めて会った頃とまるで変わらず、どこか仙人じみた雰囲気を持っている。ゆるやかに編まれた羽衣の上に長衣を羽織っているので分かりにくいが、本来右腕があるべき場所の袖はぺたんと潰れていた。
中央関係
南領・吹井郷目高の出身で、貢挙では満点を取ったことから「吹井郷の碩学」とも呼ばれる人物。かつては図書寮の御書所に所属し、禁中の書物や絵の管理を務め、綺羅絵検分の役目を担っており、版元の店主たちが下絵を持ち寄り、俵之丞がまとめて検分するのが定例となっている。地味な職務ながら、大きな失敗もなく穏やかな日々を送ってきた。
澄生に懐かれたことで、治真から声をかけられ、澄生の思惑を探ることとなる。
【容姿・風貌】
[望月の烏]での記述
名は体を表すというが、俵之丞はまさしく俵のように、矮軀でありながら丸々とした体を持つ男であった。かつてすれ違った子どもから「あのおっさん、蟇蛙みたいな面してやがる」と聞こえよがしに言われたこともあったが、生意気なクソガキに指摘されるまでもなく、己の顔面はお世辞にも整っているとは言い難いという自覚もある。
【中央城下】
富原屋の跡継ぎ。西広辻家の三男に生まれたが、西清水家当主の厚意で跡取りのいない富原屋の養子になった。
中央城下で一番古く最も規模の大きい綺羅絵の版元である本問屋『宝屋』の旦那。
【羽林天軍】
羽林天軍の兵。大滝の見張りをしている。
【中央花街】
高野太夫とともに中央花街で一番を競う青海楼の遊女である。彼女は一度登楼したものだけでなく、自分の客でもその楼閣の客でもない者のことまでよく覚えており、とても賢く貴族相手にも機知に富んだ会話を交わせることで客を楽しませている。品のある眼差しから、没落した貴族の姫様ではないかという噂がある。
北本家の若君の正室として迎えられ、お凌と呼ばれるようになる。
幼少期、高野太夫と谷間の同じ置き屋で「おゆき」として修業をしていた。
【容姿・風貌】
[きらをきそう]での記述
化粧をしていることを差し引いても異様なほどに肌が白く、しみや小さなほくろの一つも見当たらない。長いまつげを持つ目は垂れて色っぽく、小さな唇は真っ赤。艶やかに結い上げ、重たげな簪を大量に飾った髪は混じりけのない真っ黒だ。小柄ではあったが、独特の雰囲気のせいか、強烈な存在感がある。
凌霄太夫とともに中央花街で一番を競う玉兎楼の遊女である。
どんな客相手にも分け隔てなく、親しみやすく、思いやり深い接客をすることで有名で、高野太夫に会った帰り道はどんなものでも笑顔になっているということから『微笑み太夫』の別名も持っている。
幼少期、凌霄太夫と谷間の同じ置き屋で「みはる」として修業をしていた。元は宮烏の生まれだったが、花街に行く際にみはるの出自をおゆきの出自とされた。
【容姿・風貌】
[きらをきそう]での記述
格子戸から差し込む縞模様の光の中、昼間には不釣り合いな夜の花衣が、燦然と金糸を光らせている。徒人であれば負けてしまいそうな深紅の着物を、しかし彼女はさらりと着こなしていた。
白粉を透かすほどに血色がよく、頬は明るい桃色がかって、見るからに水気が多い。まさしく桃のようなやわ肌である。大きくうるんだ瞳をしていて、笑んだ瞬間に綺麗な三日月を描いたのが印象的であった。
これまで見てきたどのような女とも違う。
ほがらかでありながら闊達で、それでいて何とも女らしい。
【金雀寺(こんじゃくじ)】
谷間(たにあい)関係
地下街に住む子供。鼻が低く前歯が欠けた少年でけがや病気の責任者。
地下街に住む子供。口を一文字に結んだ気の強そうな少女で掃除等の責任者。
地下街に住む大人。元々地下街の親分衆の下で食事係をしていて、谷間襲撃の際に中央の兵と交戦し片足を失った。女房が女工場で働いている。
金烏(きんう)宗家
第一部での説明はこちら。真の金烏で猿との大戦後に正式に即位をした。一人娘である紫苑の宮を後継者にしたいと言い出し、長束らとともに進めていた。安永九年、涼暮月の三日に実の妹である藤波に背部を刺され、息を引き取る前に浜木綿の元に飛んでいき彼女の腕の中で息を引き取る。転身の最中に死んだため、通常の棺の容量に収まらず殯の後に神官たちによって解体され三つの棺に分けられた。生前手紙の入った血盟箱を大天狗に預けていた。
全て、皇后の思うように
【容姿・風貌】
[追憶の烏]での記述(雪哉視点)
線の細い女顔であり、白くすべらかな肌も、すっと通った鼻筋も、紅を塗ったように血の色を透かした唇も、若い娘御のようなみずみずしさがある。以前はその印象を払拭するかのように、ひたすらに冷たく、射抜くような眼をしていたものだったが、今の眼差しはいたって穏やかだ。
第一部での説明はこちら。幼少期には羽母がなかなか決まらず、藤宮連の滝本が教育係として育てた。その影響か、後に羽母として度々訪れる浮雲に強く懐くようになった。奈月彦の代の登殿後、心を病んでしまった。ぼうっとしたり急に泣き出す、暴れる、食事もとらずに長く眠り続けるなど、不安定な状態が続いたため、当時の大紫の御前によって静かな尼寺に預けられた。
暫くはふさぎ込んでいたが、尼寺に派遣された早蕨と話すようになり、さらに庭師の下男との交流で一時的に明るさを取り戻したが、大紫の御前にそれが知られ、庭師が交代。これをきっかけに本格的に壊れてしまう。
桜花宮に奈月彦を呼び出し、背中に懐剣を突き立てたのち、自らも欄干から飛び降りた。
【宗家従者】
第一部での説明はこちら。
第一部での説明はこちら。生まれの名はタキ。南家筋の貴族の男と下女の間に生まれた庶子で、両親を亡くして行き場を失っていたところを藤宮連として引き取られ、「滝本」の名を与えられた。もとは捺美彦の母に仕えており、その後、捺美彦に仕えるようになった。捺美彦の登殿に際しては、桜花宮の護衛を任された。藤波の宮が生まれてからは、藤波に仕え、実質的な教育係となった。藤波の宮が壊れて尼寺に身を預けられてからは、気にかけべったりと付き添っていたが早蕨が来たことによって適度な距離をとるようになる。
当時の大紫の御前から、金烏暗殺の命が早蕨を通じて下され、桜花宮に呼び出す計画に協力した。明留に腕を噛まれて動けなくなり、その顎を砕き、歯形が残った。飛び降りた藤波の亡骸を抱えてしばらく山に身を潜めていた。
医術に多少の心得があり、藤波の宮が壊れて尼寺に身を寄せていた時期に、藤宮連より派遣され付き添うようになった。藤波の心を少しずつ開かせ、会話を交わす存在となる。当時の大紫の御前から下された金烏暗殺の命を直接受け、滝本に伝える。暗殺の際には、自ら短弓を手に取り、山内衆および明留を射殺している。さらに、飛び降りた藤波を追おうとした滝本の腕に噛みついた明留の顎を砕き、逃走する手助けをした。滝本に妹がいると語った。
【容姿・風貌】
[追憶の烏]での描写
三十代と思われる、見るからに穏やかそうな女であった。
特別美人というわけではないが色白で、しっとりとした肌をした上品な女だ。笑うと頬が持ち上がり綺麗な笑窪が出来て、何とも福福しい印象となる。
第一部での説明はこちら。
第一部での説明はこちら。
東領
【東家(とうけ)】
第一部での説明はこちら
【東家従者】
第一部での説明はこちら
西領
【西家(さいけ)】
南領
【南橘家】
【南麻畑家】
安原家
安原はじめの養父。安原はじめの他に息子二人と娘一人と妻がいる。ただ、全員血は繋がっていない。
小規模な商店の店主から手広く展開した商売の一切合財が大成功を収めて一代にして巨万の富を築いたその手腕から「経済界のぬらりひょん」と呼ばれた実業家。安原はじめ以外に引き取った養子はいずれも人間的にも商業的にも大成功を収めており、人を見る目は確かである。
放浪するのが大好きで、ある程度事業が成功すると、それを人に任せふらりといなくなり何か大きな動きが起こる直前になると現れ、一見すると無茶苦茶な指示を出してまたいなくなる。残されたものがそれに従うと決まってそれが後々に大きな利益につながるという気味の悪い経営をしていた。二十年以上前に安原はじめ以外の養子に会社や事業を任せて引退している。楽園の烏(およそ2015年)より七年前に弁護士に荒山を安原はじめに遺すという手紙を預けたのを最後に行方不明。
その正体は人間ではなく、山内の谷間を自治した伝説の地下街の王、朔王である
天狗
ラフなシャツとスラックスには全く見合わない鼻高の赤い天狗面をつけた男。
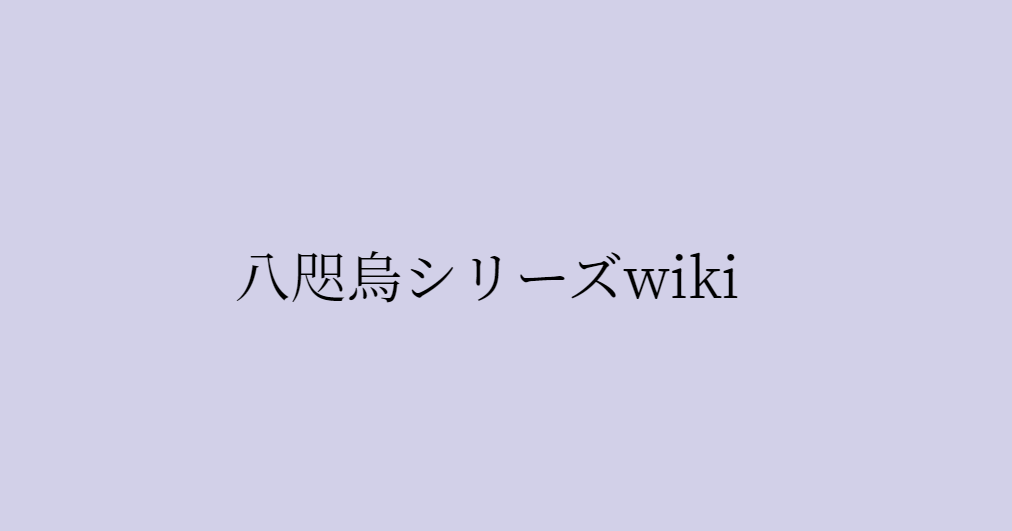
コメント
雪哉の身長は?
物語の最初らへんは大体140〜150cmくらいだと思います